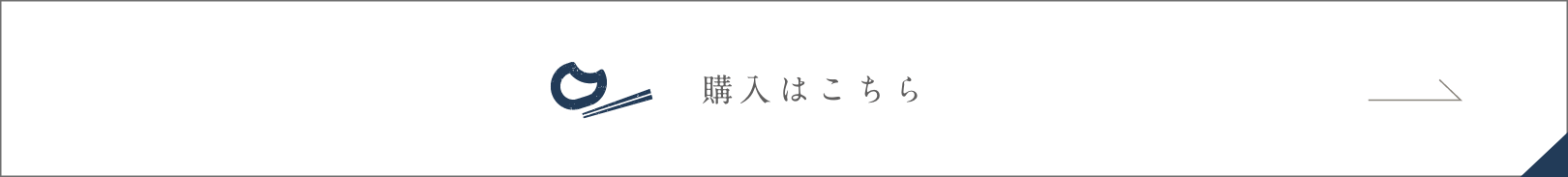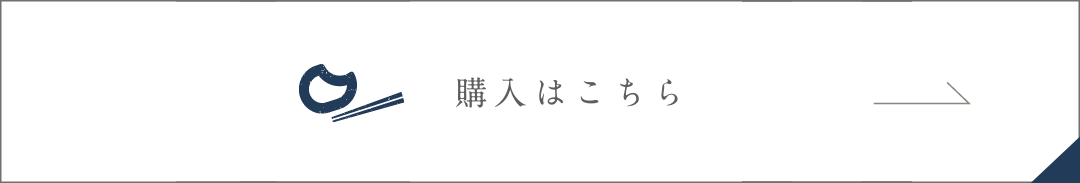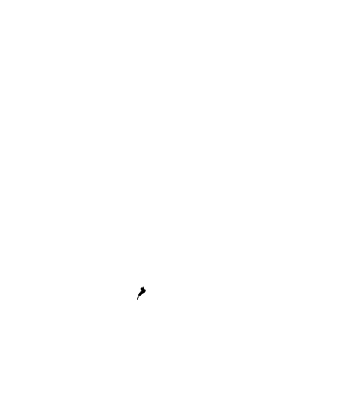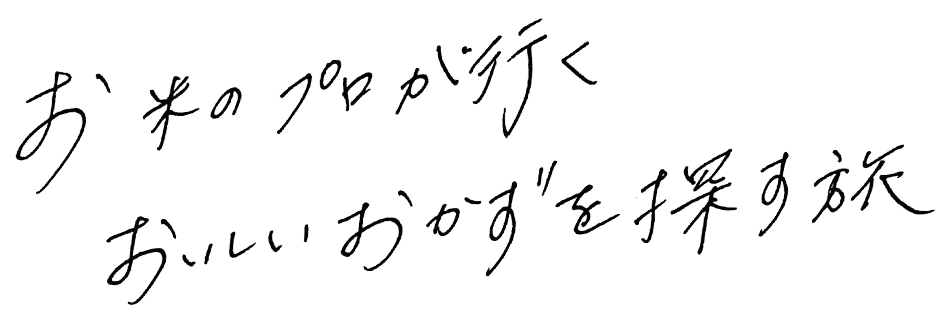能登の港町で出会った、ふわふわのおぼろ昆布
昔ながらの製法で仕上げる、極上のご飯のお供
大脇昆布
石川県鳳珠郡能登町宇出津山分4-63-2

シュッ、シュッ、シュッ…。少しひんやりとした静かな加工場で響くのは、皮つきの昆布が専用の包丁で削られていく音。「太白おぼろ昆布」を伝統製法で作り続ける「大脇昆布」の大脇一登さんの工場を初めて訪れたのは数年前のこと。
この度、ご飯に合う美味しいおかずを探し求める日々を経て、ようやく皆さまにお披露目する「おかずサイト」が完成しましたが、この連載をスタートする僕が、まず始めにご紹介したかったのが、ここ「大脇昆布」さんでした。ごはんにあう、最もシンプルなおかずは何か?と考えた時、真っ先に大脇さんが浮かんできたことから、久しぶりに訪れてみたくなったのです。ごはんにのせても、おにぎりに巻いても美味しい「おぼろ昆布」。その美味しさの秘密を見つけにきました。
-

最高級の昆布で作られる「おぼろ昆布」。大脇さんは、北海道函館市の真昆布を使っています。
-

「おぼろ昆布」の伝統的な手すき製法。シュッ、シュッと独特な音は、昆布を下から削り上げるときに響いてきます。
能登町宇出津は、小さな港町
大脇昆布はその小高い丘にあります
「大脇昆布」は、石川県能登町にあり、僕らの米屋がある石川県野々市市から、北へ約130キロ。「のと里山海道」を利用して、2時間ほどかかります。石川県民として産まれ育った僕も、同じ県にありながら気軽に足を運べるような地域ではない遠い場所。冬の終わりとはいえ、小雨がちらつく午前中についた能登町は、手がかじかむほど寒く、日本海からの冷たい風が丘に向かって吹いていました。
能登半島の地形は、SNSの「いいね!」や「Good」でお馴染みのグーサインの親指のようなカタチをしています。凍てつく冬と、日本海の荒波や断崖絶壁といった厳しい環境をイメージする人も多いと思いますが、そんな厳しい自然の中に、生きる人の営みがあるからこそ、美しい自然が保たれているように、僕は感じています。
そして、能登半島の外側の付け根のほうにあり、小さな漁港がいくつもある能登町宇出津(ノトチョウウシツ)にも、静かな人の営みがありました。その港町を見下ろす、小高い丘にある、大脇昆布さん。
久しぶりに訪れた加工場は、ほんのりと酢の香りがしていました。静かな工場で響く、昆布を削る音は、前回よりも鮮明に聞こえる気がしました。
-

薄く削られた昆布は、美しく透き通っていました。厚みはたったの約0.4mmだそうです。
-

出来立ての「太白おぼろ昆布」はふわふわで、柔らかく、溶けてなくなりそうでした。
最高級の昆布で作られる「おぼろ昆布」
函館の真昆布は甘みと旨味が凝縮され、分厚さが特徴
あつあつの白ご飯の上にのせても美味しい、出汁をとっても美味しい昆布は、日本人の僕らの生活には欠かせないものですよね。その昆布の中でも、最上級といわれる「おぼろ昆布」。あまり馴染みがないという方もいらっしゃるかもしれませんが、僕も「おぼろ昆布」がどのように作られているのか、ほとんど知りませんでした。
食べる昆布の中では、とろろ昆布のほうが、身近な存在だと思います。「おぼろ昆布」と「とろろ昆布」、名前もどことなく近いですが、いったい何が違うのか。それはずばり、製法の違いによるものだったのです。昆布の種類の名前ではないのですね。
製法の違いというのは、昆布の削り方のこと。
「おぼろ昆布」は、熟練の職人が皮つきの昆布の表面を一枚一枚丹念に削り上げたもの。「とろろ昆布」は、昆布を何枚にも重ねて圧力をかけた束の昆布を機械で削ったもの。
似ているようで、全くことなる製法で、見た目も味わいもまったく違うものになります。もちろん、使う昆布の種類もことなります。
「おぼろ昆布」は、昆布の表面を、専用の包丁で丁寧に1枚1枚削り上げるので、昆布に一定の厚みがあってデコボコがないものでないと作ることができません。肉厚で平らであるというのは、最高級の昆布の証だということです。
大脇さんが昆布を削る姿は力強さと繊細さが同居していて、とても美しく見えました。昆布を押さえる右足と包丁を持つ左手のバランス。薄くなるにつれ、少しずつ変わる動き。昆布が上下する様子は、まるで波のようでした。
大脇さんが使うのは、北海道函館の真昆布で一等級のブランド昆布です。大脇さん曰く「おぼろ昆布」に最適な、厚みがあるのがいいのだとか。昆布には出汁をとるためのものや乾燥させておやつするものや昆布加工品など、さまざまな種類がありますが、「おぼろ昆布」にマッチした昆布があるのですね。「おぼろ昆布」は、まず昆布を柔らかくするためお酢に少しだけ漬けます。酢の加減は季節や天候に寄って決めるのだとか。その後、ひと晩寝かせると、白い粉を吹きます。これが養分だそうです。乾燥させてから、専用の包丁を使って削っていくのですが、魚の鱗をとるようにまず、昆布の表面の苦味や酸味を削っておきます。そして、その中から出てくるのが、本当の美味しい、昆布の“肉”の部分です。この部分の味わいは格別。僕も削りたての昆布をいただきましたが、思わず頬が落ちるかと思いました。
そして大脇昆布の看板商品「太白(たいはく)おぼろ」は、昆布の芯の白い部分だけを削ったもので、マグロで言うトロのようなところ。ふわっととろけ、自然の甘さが口に広がります。ちなみに、最後に残った昆布の芯の部分はバッテラ寿司や押しすしに使われるそうです。
-

匠の技を近くで見させていただきました。美しく削られた昆布は、まるで芸術品のようです。
削りつつけて35年、
大脇さんの全ての想いが「おぼろ昆布」に宿る
「伝統製法を守っていきたい」
大脇さんが昆布を削り始めたのは約35年前。お父様が営んでおられた昆布加工業を子供の頃から見て育ったとのこと。自然と、「おぼろ昆布削りの職人」になる道を選ぶことになります。そして、この昔ながらの伝統製法を守り続けようと決心し、若い頃から修業に励んでいたそうです。先代の社長は、手すきおぼろ昆布の生産量が全国の80%以上を占める福井県敦賀市で修業を重ねたのち、故郷の能登へ戻り、大脇昆布を創業したそうで、そのころは、おぼろ昆布削り職人も多いときは、7人ほどいらしたとか。でも、昆布削りはとても骨の折れる仕事で、熟練の職人になるには、3年から5年ほどかかるため、なかなか若い職人が育たなかったそうです。そして今では、「大脇昆布」の社長である、大脇一登さんが、お一人で削っています。なんと県内の「おぼろ昆布削りの職人」は大脇さんお一人しかいないとか。
全国的にも職人の減少が深刻な問題となっているようで、ピークの10分の1の数になってしまったそうです。同じ姿勢で何時間も昆布を削るのは確かに根気がいりますし、高齢化になってしまうことも納得してしまうほどでした。
それでも大脇さんは現在、その伝統の技を守り続けようと、様々な活動を続けられています。なんと20年以上も全国の百貨店の物産展に出向いて『手削りおぼろ昆布の実演』を行っているのです。実演や昆布削りの体験を通じて、昆布を身近に感じてもらいたい、という強い願いと、昆布の需要減少、現代人の食生活にる昆布離れという危機意識から、活動を続けているそうです。僕ら米屋が抱える問題“若者のコメ離れ”という社会問題にも通ずるものがあると感じ、頭が下がる思いがしました。
-

「伝統の技を守り続けていくことが、私たちの大事な事業」と語る、社長の大脇一登さん。
-

昆布を削るには、包丁の砥ぎや手入れが欠かせない。座る椅子や台にも大脇さんの熱い思いを感じます。
-

熱々のごはんにのせたら、溶けてしまいそうな薄い昆布絹のように薄く柔らかい食感にもかかわらず、旨味が濃く、食欲のない日でも、お代わりできそうです。
近年は、昆布を使ったふりかけなどの新商品を次々と開発されている大脇昆布さん。テレビや雑誌などのメディアで取り上げられることも増えているようです。昆布を身近に感じてもらおうと開発した「KOMBU MAGIC(コンブマジック)シリーズ」は、これまでのお客様の声を活かして、用途や利用シーンをイメージさせ、使いきれるようなサイズにするという戦略でヒット商品となったふりかけです。「ごはんにかけて食べるこんぶ」「酢の物に和えるこんぶ」など多くのアイテムが出揃うなか、キラーアイテムとなったヒット商品は「トーストにかけて食べるこんぶ」。僕としては、「ごはん」にかけてほしいけど(笑)。

取材に快く応じてくださった大脇一登さん、弘子さんご夫婦。お二人で伝統の技を守りながら、新しい挑戦をなさっています。大柄で朗らかな笑顔の一登さんのお人柄を、醸し出すような優しい味わいの昆布。これからも応援します!